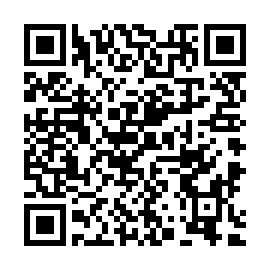2月18日は嫌煙権運動発足の日です。
2月18日に発行される『みんなの嫌煙権」に当会副代表の荻野が寄稿しました。

出典:『みんなの嫌煙権』No.16(2015年2月18日、嫌煙権確立をめざす人びとの会)
写真では読みにくいため、以下、全文を掲載します(許可取得済み)。
少々校正が甘い箇所があることと、段落設定の問題により掲載紙と段組みが異なる点は、何卒ご容赦ください。
未来世代へタバコのない社会を
~勇気もらった嫌煙権運動~
喫煙を考える代表 荻野寿美子
「嫌煙権運動」の旗揚げからもうすぐ半世紀、その間、「嫌煙権運動」を報道などで知り、意思表示する勇気、行動に移す勇気、不断の努力に必要な不屈の勇気をもらった人は多いと思います。
実は私もそのなかの一人です。家庭内での受動喫煙に物心ついた時から苦しんできた私は、ニュースで知った嫌煙権運動に勇気づけられ、禁煙マークを描いた札に「この部屋でタバコは吸えません」と書いて自室のドアに掲げました。
普段は紳士で優しいにもかかわらず、ことタバコに関しては手前勝手な暴君に変貌する父が、それ以来タバコを吸いながら私の部屋に入って来ることはなくなりました。
父の脚に取りついて「苦しいからタバコをやめて」と泣いて訴えるだけだった子どもに、別の方法があることを「嫌煙権運動」は教えてくれたのです。
■住宅での受動喫煙問題
「嫌煙権運動」をはじめタバコ問題を解決するために活動してきた皆さんの不断の努力により、禁煙の場所が乗り物や病院、学校などへと徐々に広がり、医療関係者や市民団体の皆さんの禁煙・卒煙の働きかけや継続した子どもたちへの防煙教育は、喫煙率の低下をもたらしました。
その一方で、家庭内での受動喫煙に苦しんでいる子どもは、現在でも少なくありません。
外からは見えにくい場所で、かつての私と同じように苦しんでいる子どもがいるかと思うと、胸が潰れそうになります。
さらには、家庭内の範囲を越えて及ぶ、近隣からの受動喫煙被害に遭う人も増加しています。
被害家庭の子どもが喘息になったという話も耳にします。被害者は体調悪化を抱えながら解決策を探し求めて右往左往する一方、相談を受けた先では対応に苦慮し、最終的には個人間の問題だとしてお手上げ状態になる事例も散見されます。
そこで、住宅での受動喫煙問題を少しでも解決に近づけるため、昨年1月に兵庫県在住の方と「住宅での受動喫煙被害を考える会・兵庫」(https://tobacco-higai.com/)を立ち上げました。私的空間の喫煙であっても他者に受動喫煙をさせることのない住環境の実現をめざして、副代表として持てる力を尽くしたいと考えています。
■未来世代への責務
感染症の流行や環境汚染、気候危機、そして貧困…。最も影響を受けるのは、社会的に弱い立場に立たされている人々です。子どもはその最たるもので、過去の大人たちが作り上げてきた社会構造のただなかに生み落とされ、大人が選択してきた結果を引き継がざるを得ません。
たばこ産業の発展と財政収入の安定的確保を目的としたたばこ事業法を有し、財務大臣が大株主となってタバコ企業を保護している本邦では、地方行政までもがたばこ税収を確保するためタバコ産業と協働して喫煙環境を整備し、喫煙防止キャンペーンを後援して次世代喫煙者の増加に加担するばかりか、それらをあたかも「いいこと」に見せかけようとしています。
しかし、そうした欺瞞的構造を構築したのが大人なら、変えることができるのも大人なのです。
「お金のために、私たちよりタバコの方が大切だったのだ…」と未来世代を失望させることがないように、タバコのない社会をつくる責務が大人にはあるのです。
【おぎの・すみこ=住宅での受動喫煙被害を考える会・兵庫 副代表】